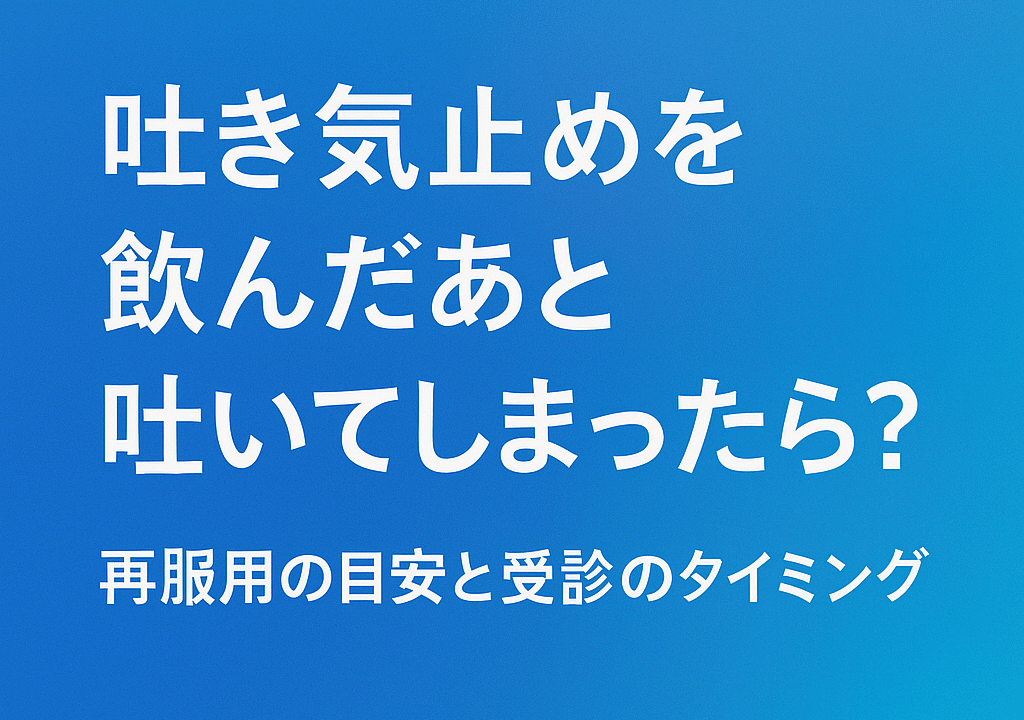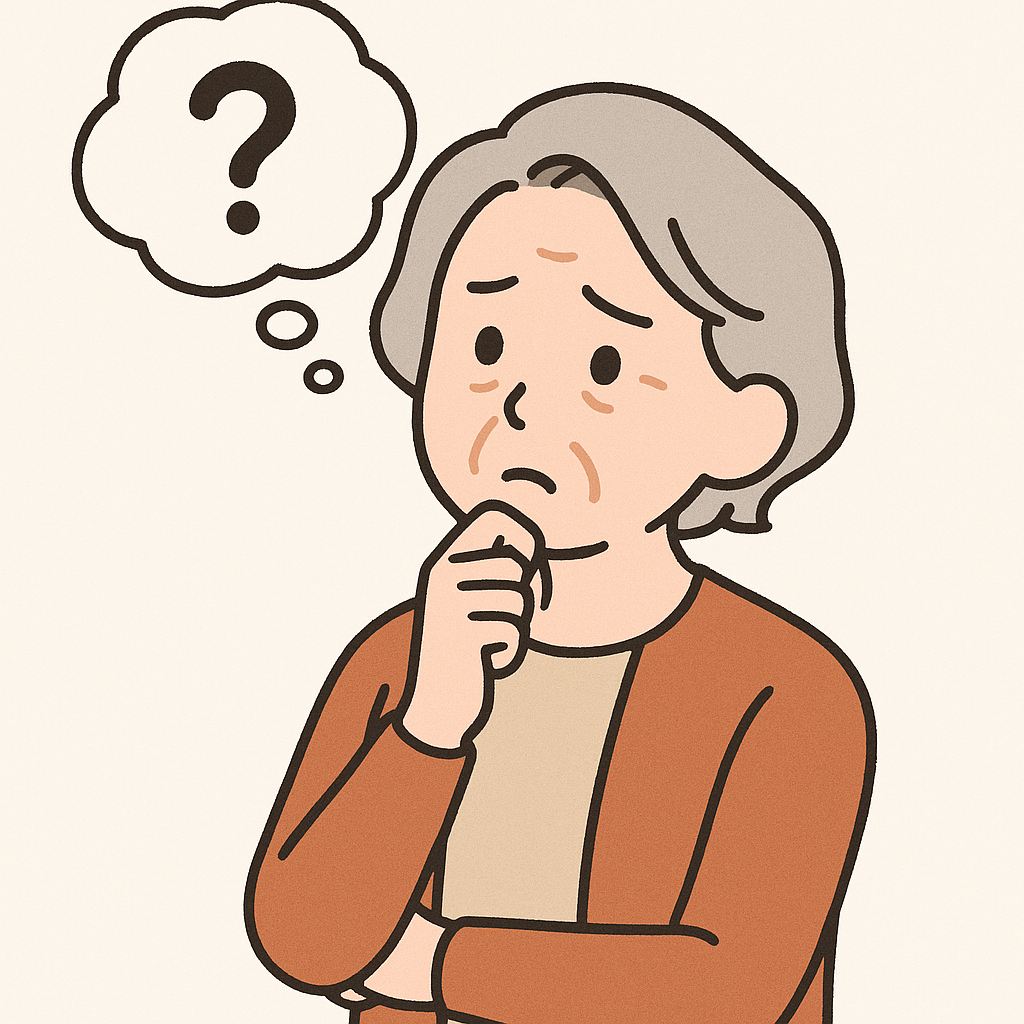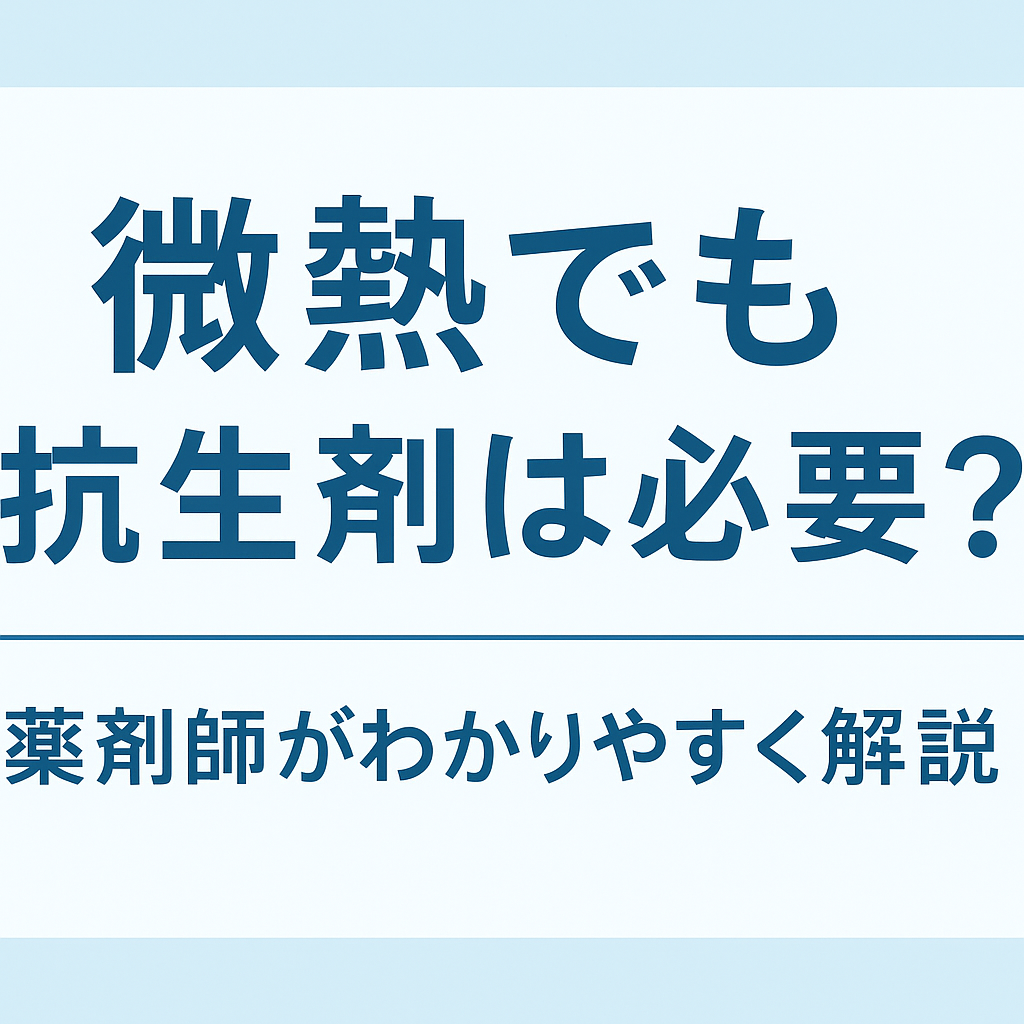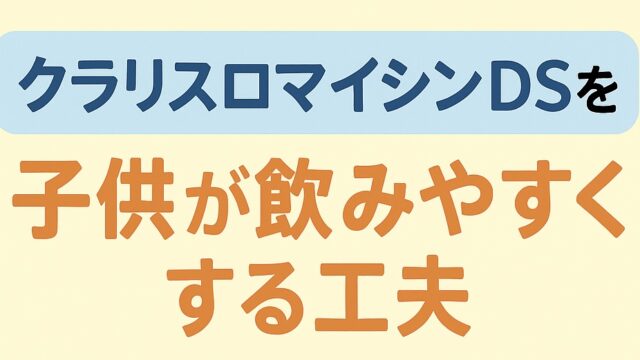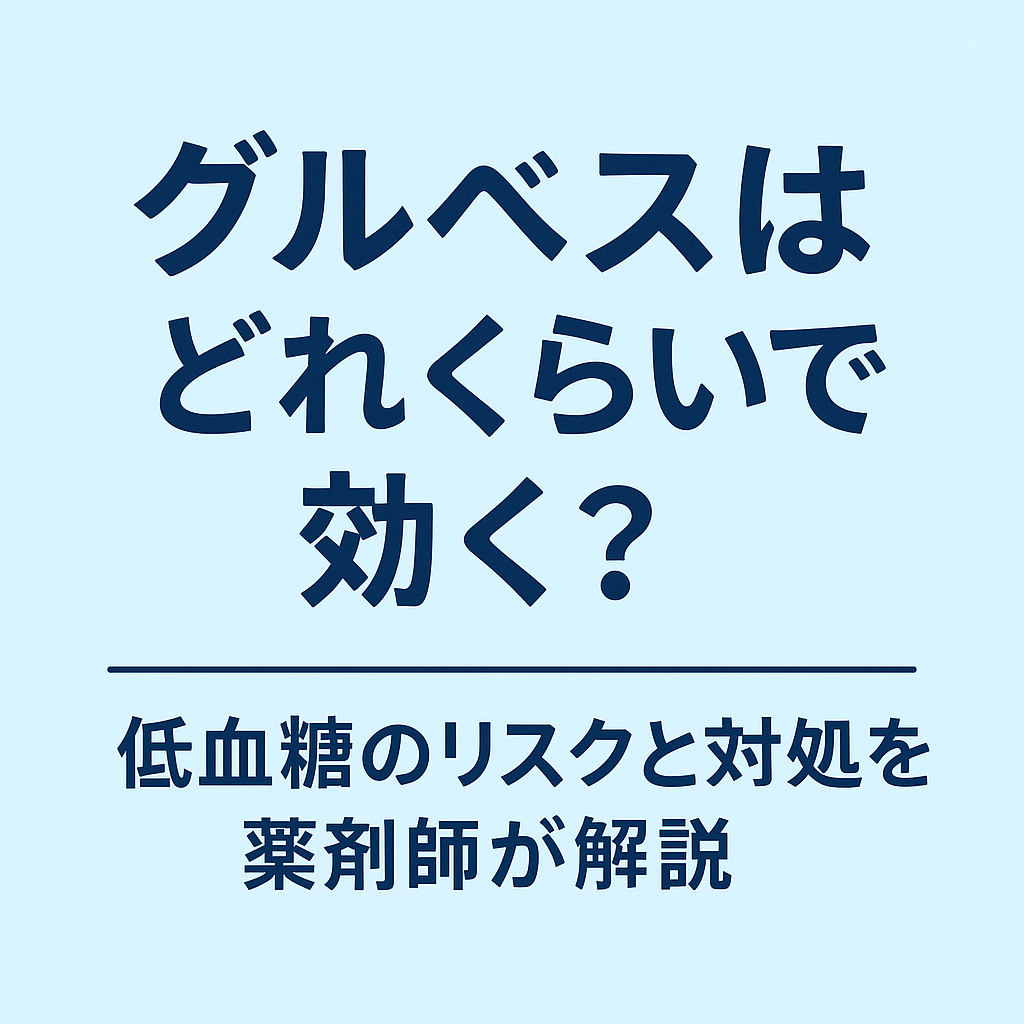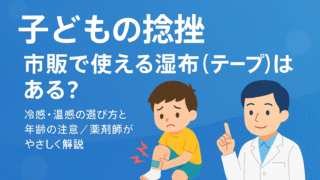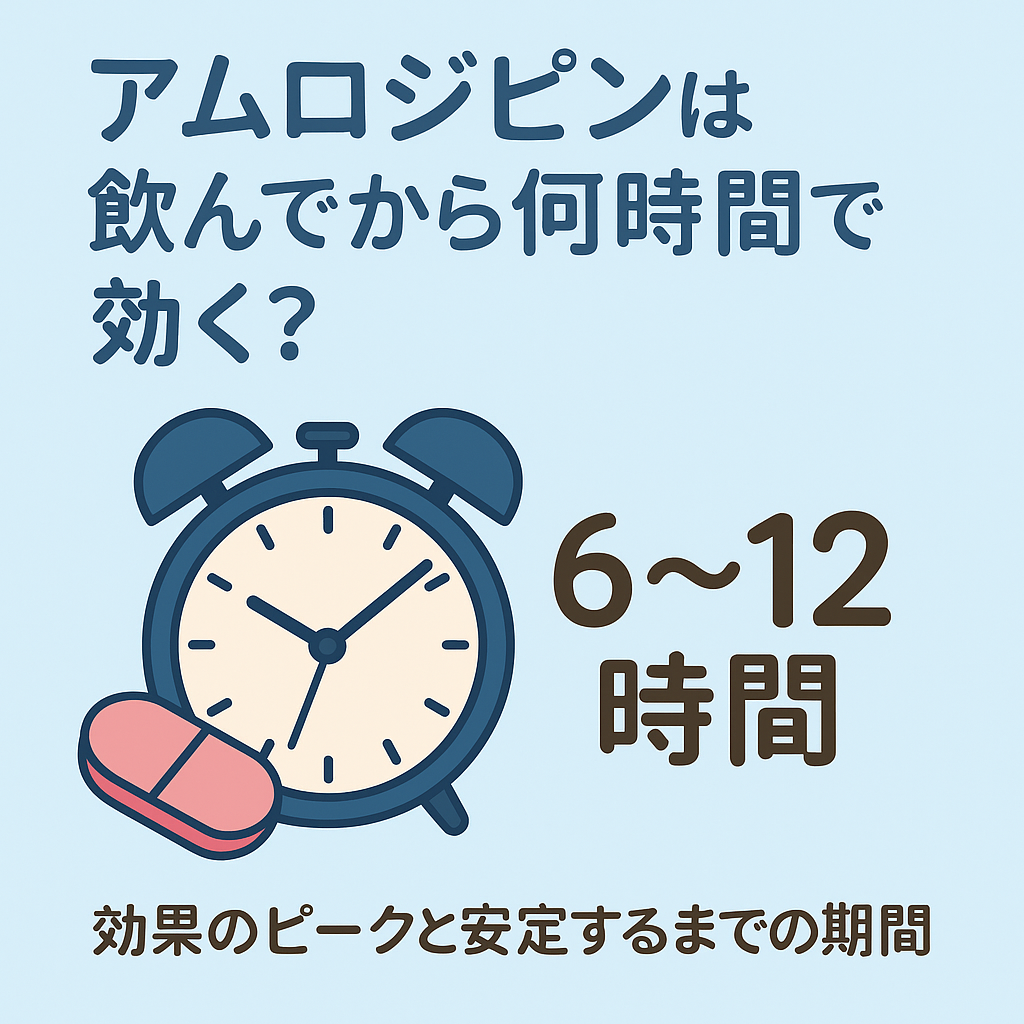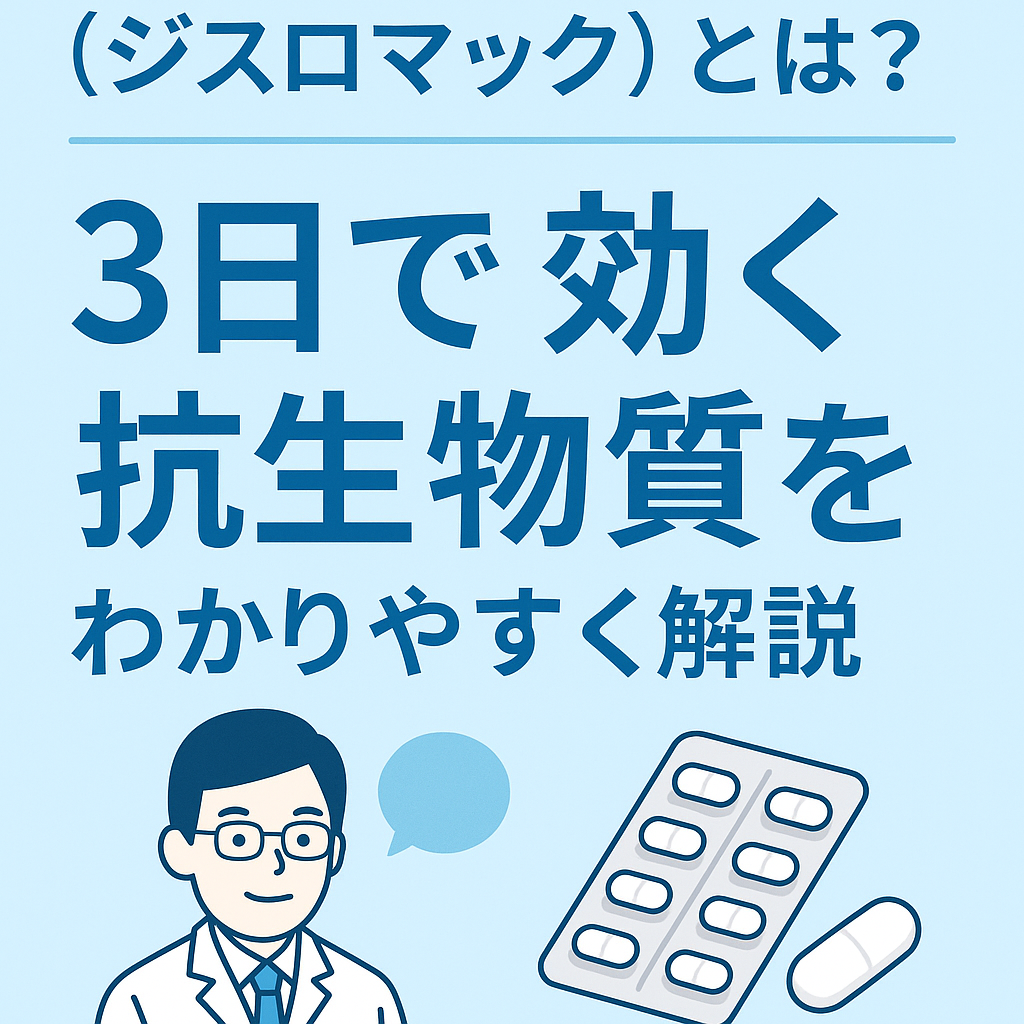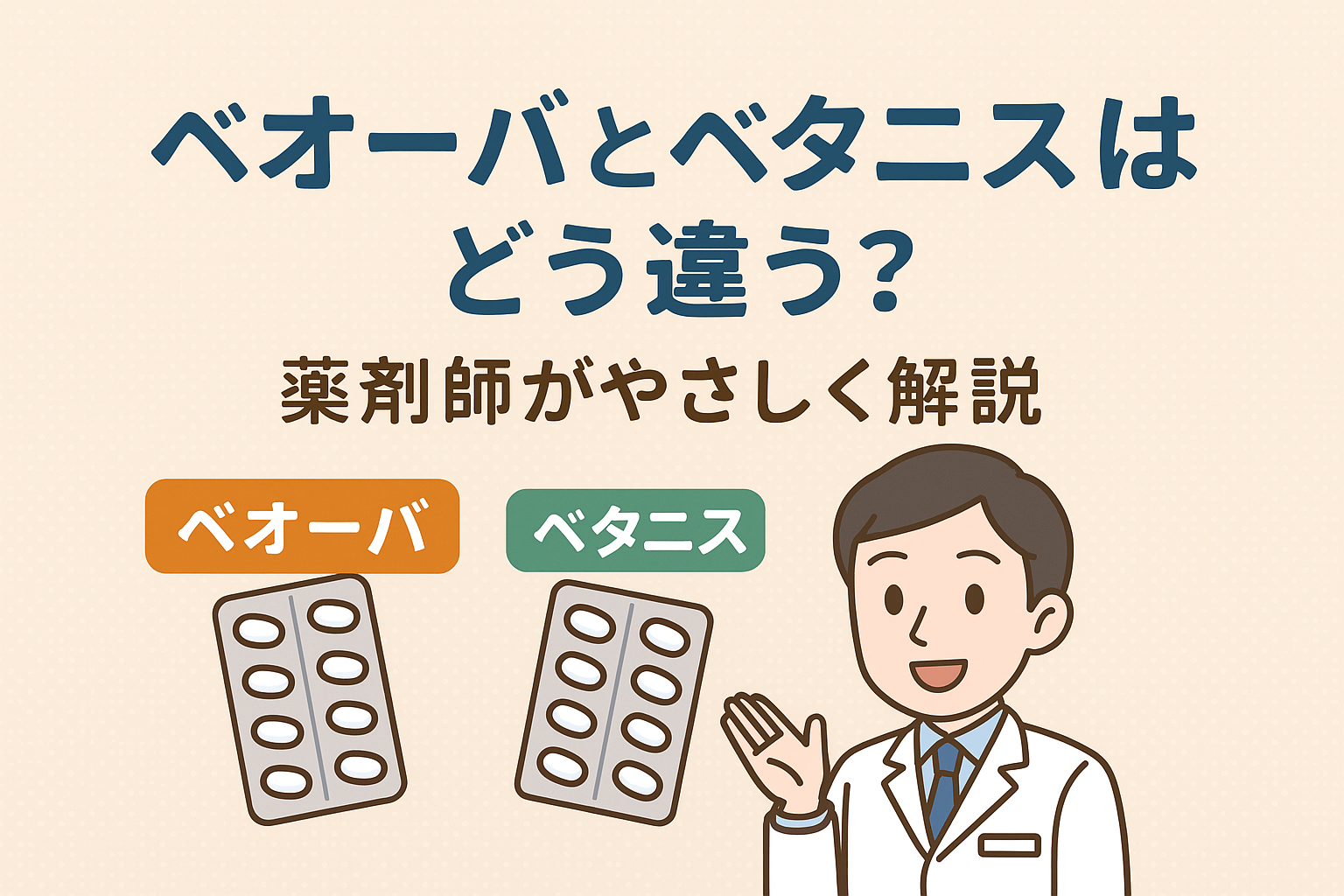吐き気止めを飲んだあと吐いてしまった…もう一度飲む?
「せっかく飲んだのに出ちゃった…」と不安になりますよね。結論は“飲んでからの経過時間”と“その後の体調”で判断が変わります。会話形式で、落ち着いて確認していきましょう。
🧑🦰
患者さん
吐き気止めを飲んだんですが、そのあとすぐ吐いちゃって…どうしたらいいですか?
🧑⚕️
薬剤師
大丈夫、落ち着いていきましょう。まずは飲んでからどのくらいで吐いたかを教えてください。目安を下にまとめますね。
① 15〜30分以内
- 薬はほとんど吸収されていない可能性が高いです。
- 自己判断での追加服用は控え、処方先(病院/薬局)へ連絡し、追加で飲む指示が必要か確認しましょう。
- 吐物の中に錠剤や顆粒がそのまま見えると未吸収の可能性がより高いです。
② 30〜60分
- 一部は吸収されている可能性があります。
- 過量になる恐れがあるため、追加服用は指示がある時のみに。
- まずは少量ずつの水分(スプーン1〜2杯)で落ち着かせましょう。
③ 60分以上
- 多くは吸収済みと考えられます。
- 基本は次の服用時間まで待つのが安全です(医師から別指示がある場合はそれに従う)。
- 吐き気が続く・水分も保てない時は受診を検討しましょう。
まずはここから
- 水分は少量ずつ(5〜10分おきにひと口)。経口補水液や薄めのスポーツドリンクも◎。
- 匂い・刺激が強い飲食は控え、落ち着いてから消化にやさしいもの(おかゆ、うどん、ゼリーなど)へ。
- 再び吐きやすい時は、坐剤・舌下/頬粘膜で溶かすタイプ・点滴など、飲まない方法に切り替えられることも。次回受診時に相談しましょう。
※ がん治療などで吐き気止めの事前投与スケジュールがある方は、必ず担当医の指示を最優先してください。
つぎのような時は医療機関へ
- 水分がほとんど取れない/尿が極端に少ない・濃い、口が乾く、ふらつくなど脱水サインがある
- 強い腹痛、吐血/黒い便、激しい頭痛、意識がもうろう
- 半日〜1日以上、嘔吐が続く/悪化している
- 乳幼児・高齢者・妊娠中・持病や多剤併用の方で心配がある
自己判断で避けたいこと
- 「出てしまったから」とすぐ同じ薬を重ねて飲む(過量の恐れ)
- 大量の水で流し込む(胃が膨れて余計に吐きやすくなる)
- アルコールや強い炭酸、脂っこい食事をすぐ摂る
よくある質問(FAQ)
Q. 吐いたあと、同じ吐き気止めをもう一度飲んでいい?
経過時間で変わります。15〜30分以内なら未吸収の可能性が高いですが、薬の種類や用量によって対応が違うため、処方先へ連絡し指示を確認してください。60分以上なら多くは吸収済みと考え、原則は次回まで待機が安全です。
Q. 吐いたけど、薬が出たか分からない…
吐物に薬の形が残っていると未吸収の可能性が高いです。判断に迷う場合は、服用時間と症状の経過をメモして病院/薬局に相談を。
Q. すぐ吐いてしまう体質。飲まない方法はある?
あります。坐剤や舌下・頬粘膜で溶かすタイプ、点滴などに切り替えられる場合があります。処方目的(乗り物酔い、胃腸炎、片頭痛、抗がん剤など)により最適が異なるため、受診時に相談してください。
Q. 子どもが嘔吐。吐き気止めは使っていい?
小児は年齢・体重で用量が変わり、脱水リスクが高いため自己判断は危険です。口が渇く・尿が少ない・ぐったりなどがあれば早めに受診を。服用前に必ず医療者へ相談しましょう。
Q. 次に同じことが起きないコツは?
- 匂い・刺激の少ない環境で、少量の水で服用
- 服用前後は一度に大量の飲食を避ける
- 吐き気の原因(乗り物酔い・片頭痛・胃腸炎など)に合わせ、予防的なタイミングで使う
まとめ
- 15〜30分以内に吐いた:未吸収の可能性が高い → 自己判断で重ね飲みせず、処方先へ連絡。
- 30〜60分:一部吸収の可能性 → 追加は指示があるときのみ。少量の水分で安静。
- 60分以上:多くは吸収済み → 基本は次回まで待つ。続く嘔吐や脱水サインなら受診。
迷ったら
「服用時刻」「吐いた時刻」「吐いた回数」「水分がとれているか」をメモして、処方元へ電話相談するとスムーズです。
本記事は一般的な目安です。処方内容や基礎疾患により対応は異なります。必ず医師・薬剤師の指示を優先してください。