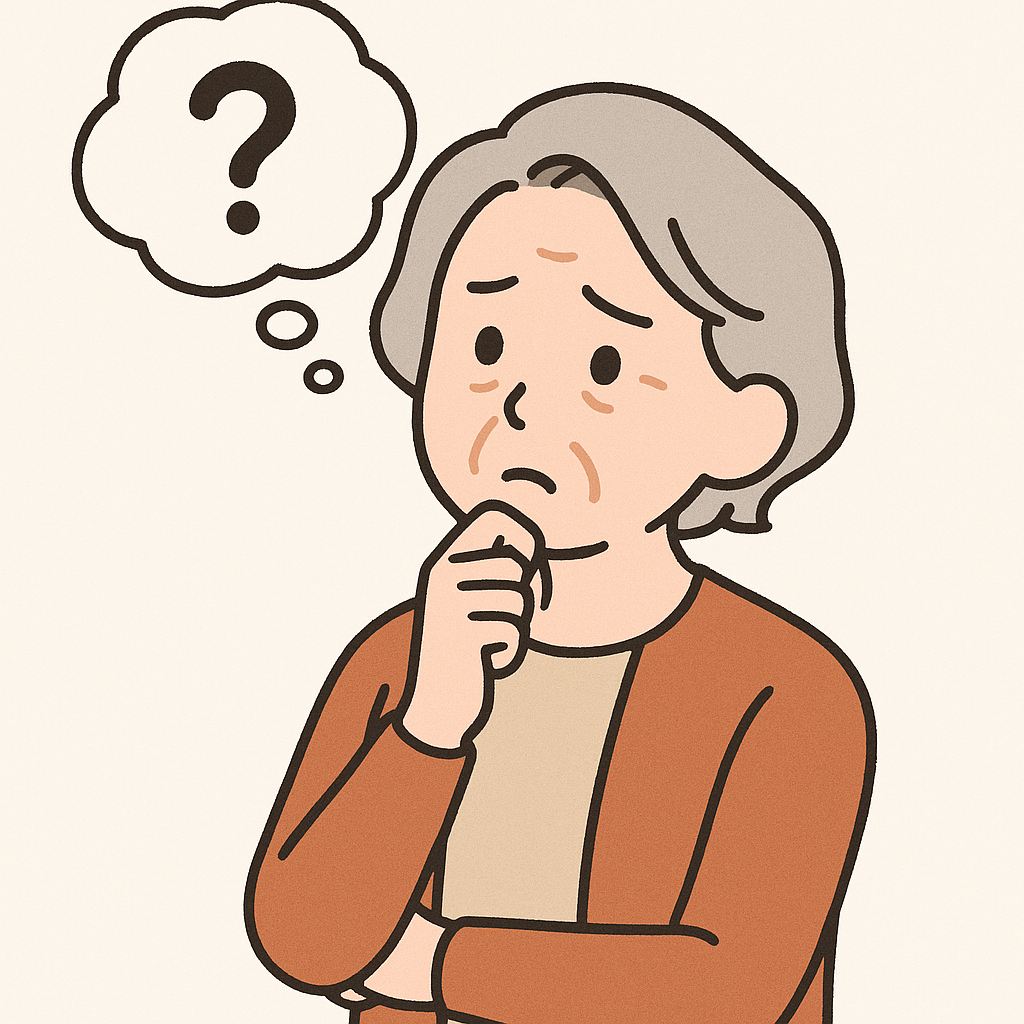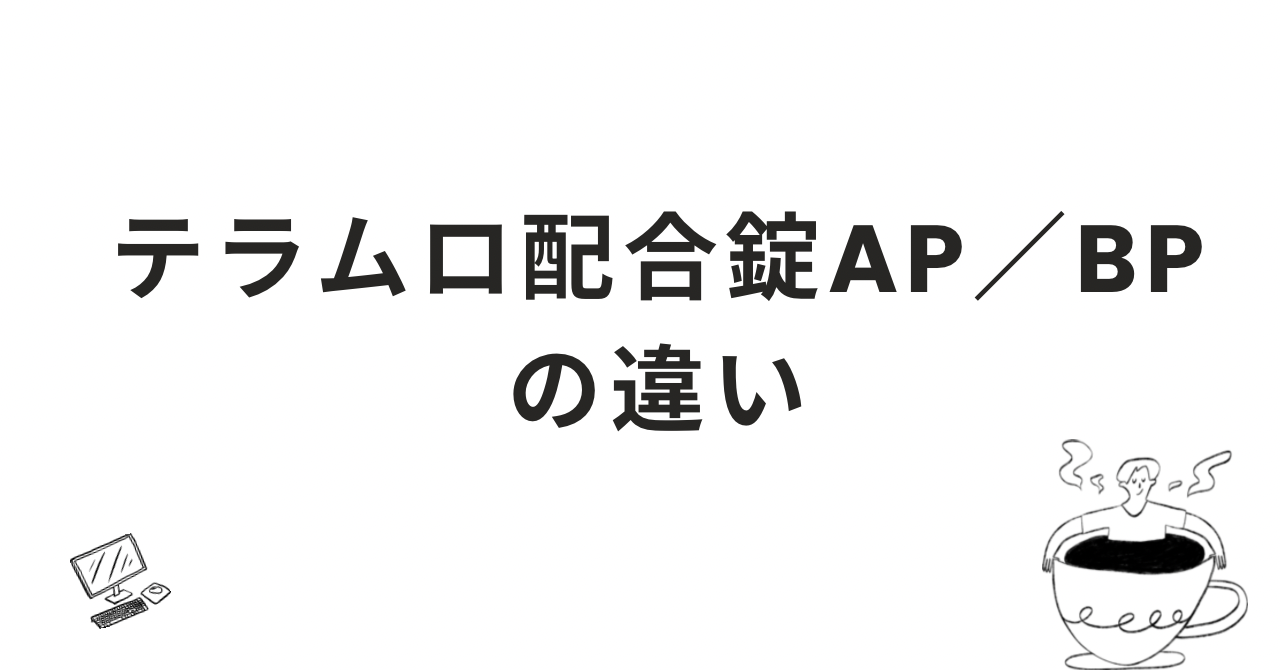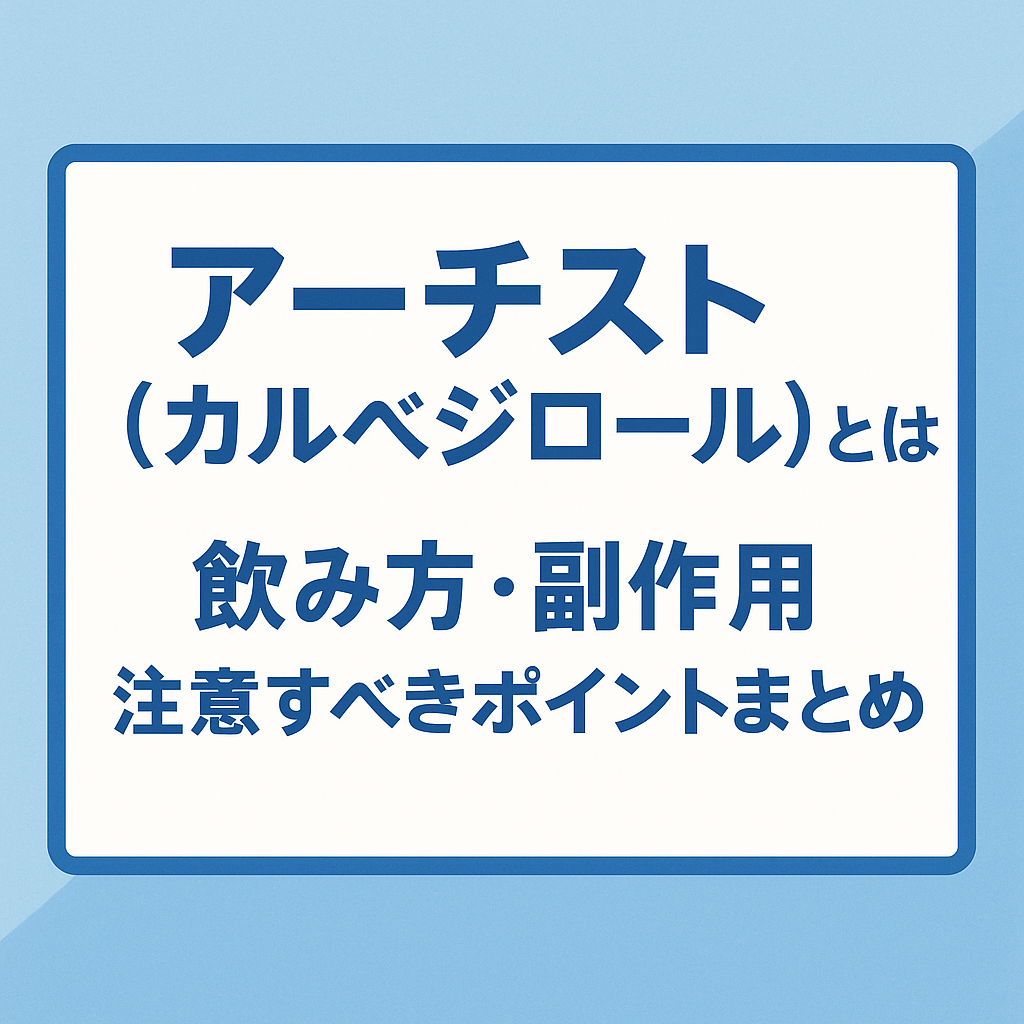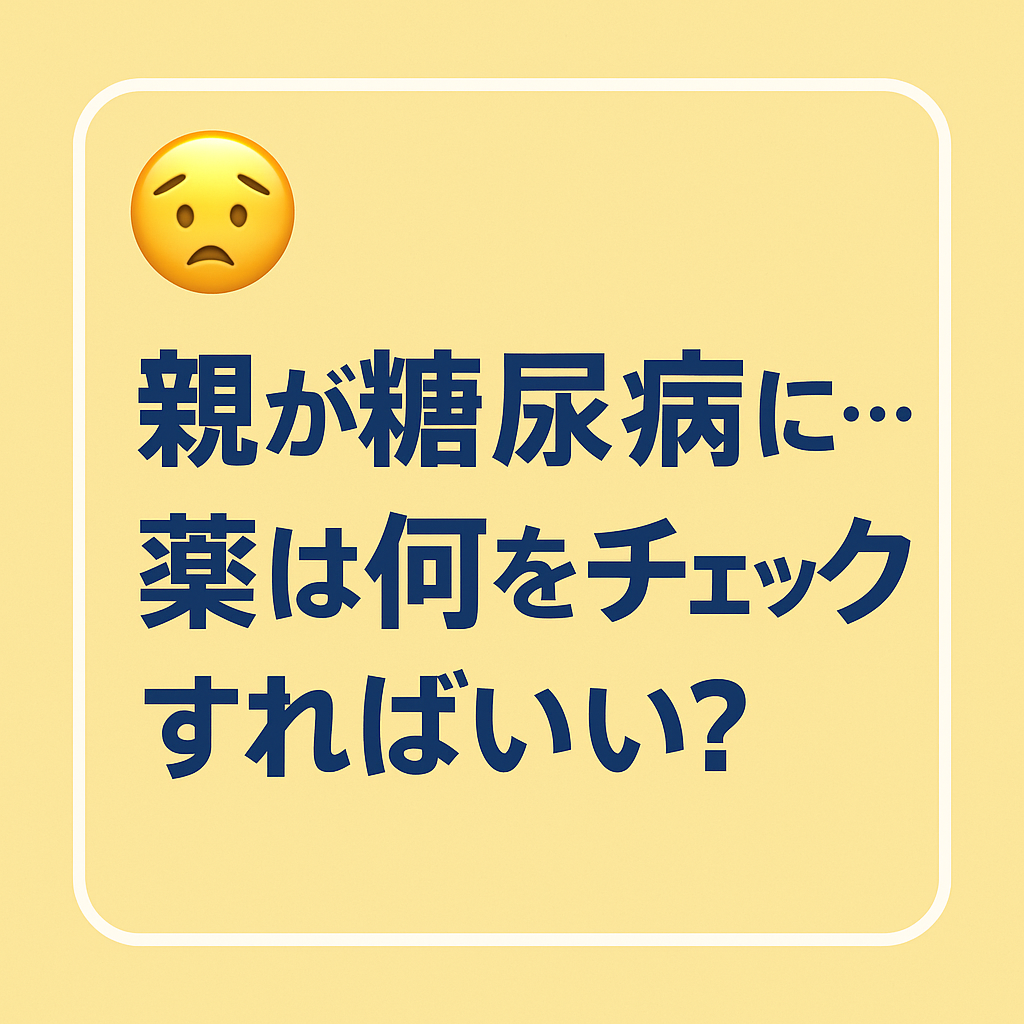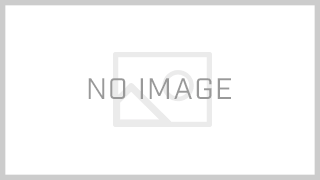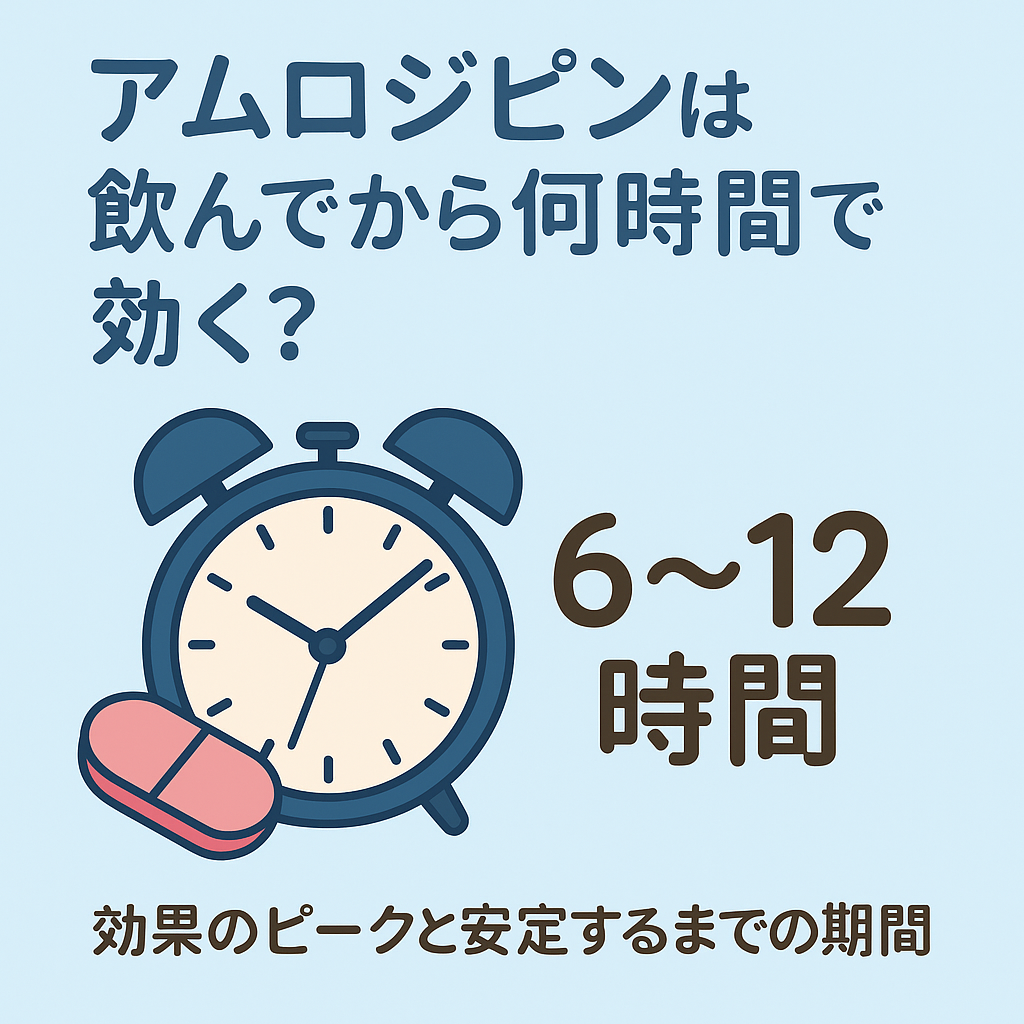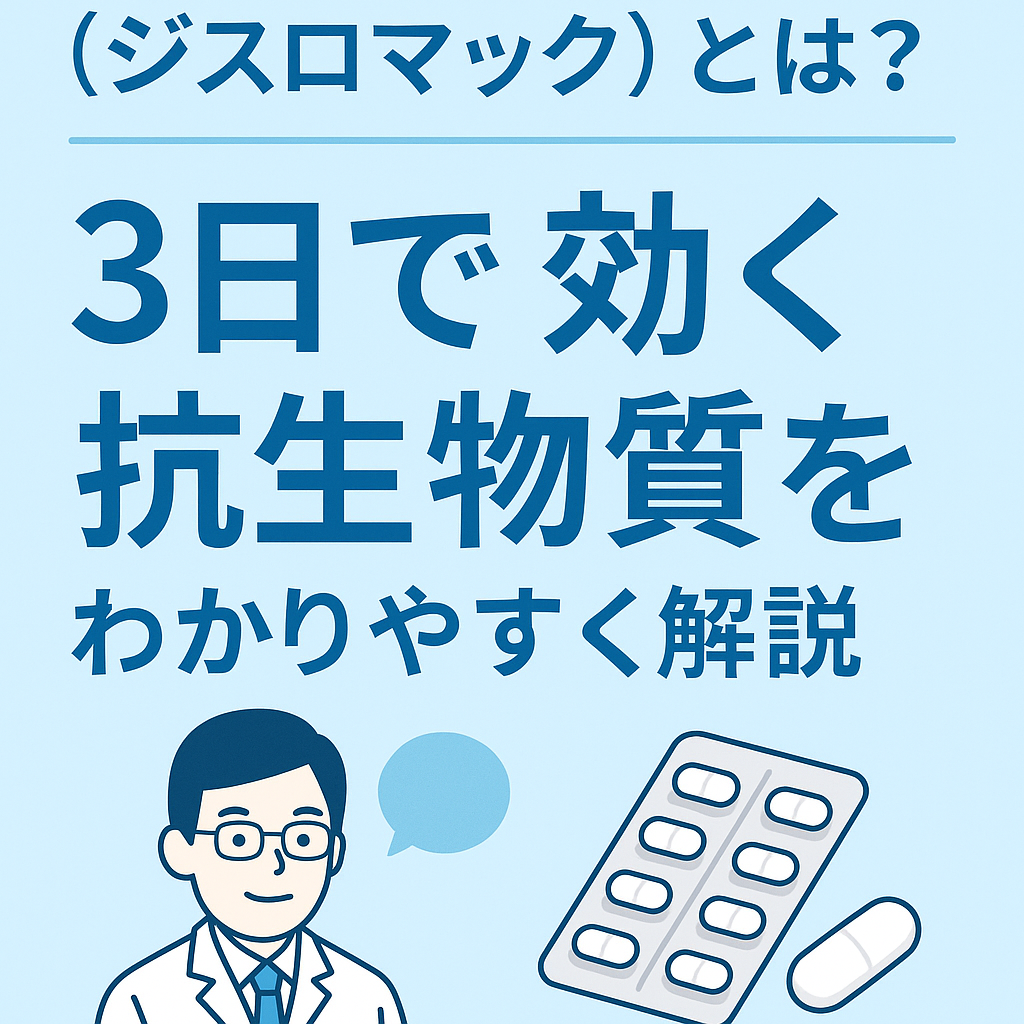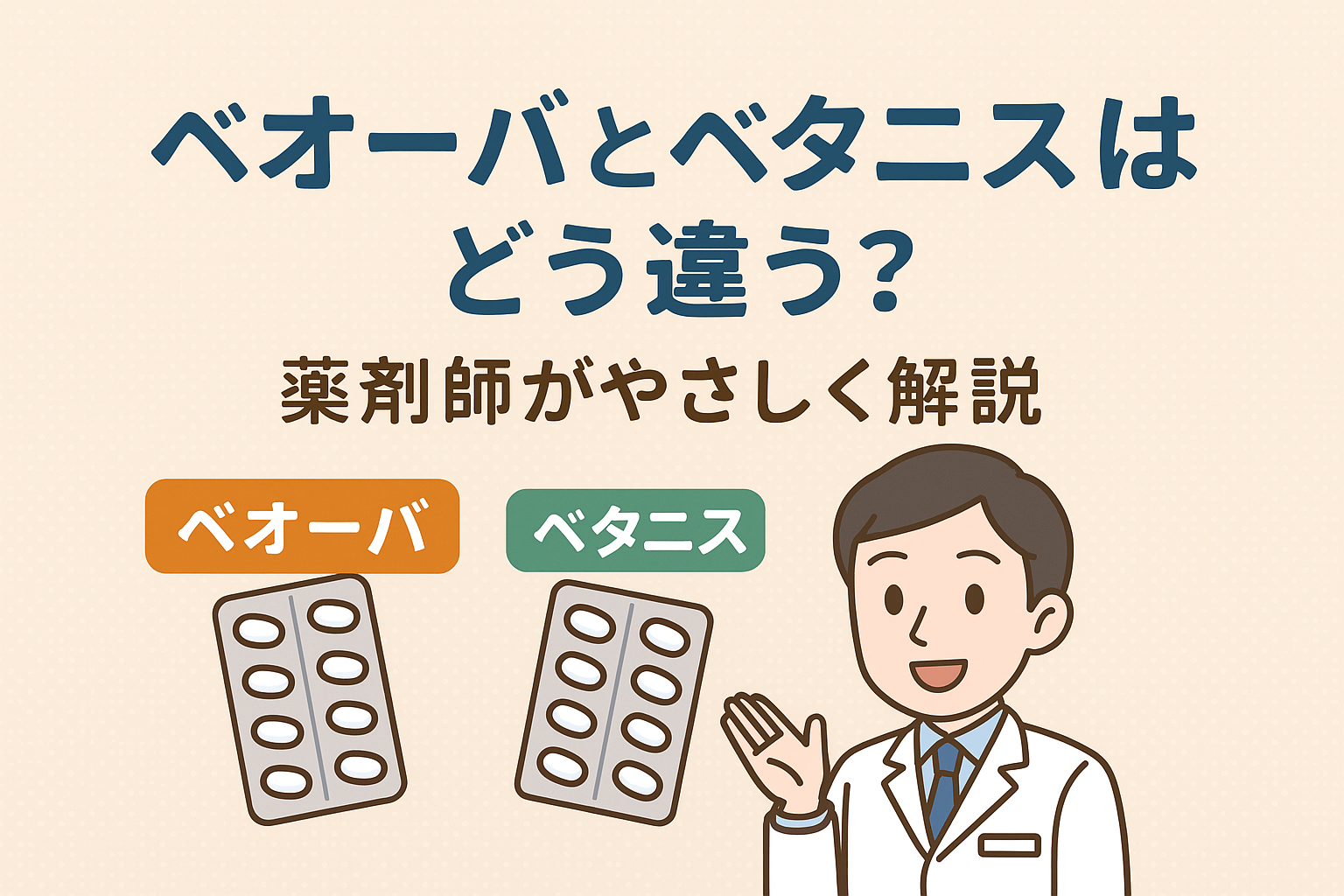患者さん向け
降圧薬、どれがどう効く?薬剤師がやさしく徹底解説【会話形式】
「種類が多くて覚えられない…」という声に、会話でスッと入る整理法。副作用や飲み方のコツもまとめました。
この記事でわかること
- 降圧薬を「どこに効くか」で4群に整理
- 代表薬・よくある副作用・向いている場面
- 毎日続けるためのコツと自己管理のポイント
目次
会話で理解する:まずは全体像
患者さん
薬の名前が難しくて…結局どれがどう効くのか分からないんです。
薬の名前が難しくて…結局どれがどう効くのか分からないんです。
薬剤師
大丈夫。「どこに効くか」で整理すると一気にわかりやすくなります。
①血管を広げる、②心臓の働きをゆるめる、③体の水分を減らす、④神経の指令を弱める——この4つが軸です。
大丈夫。「どこに効くか」で整理すると一気にわかりやすくなります。
①血管を広げる、②心臓の働きをゆるめる、③体の水分を減らす、④神経の指令を弱める——この4つが軸です。
患者さん
ホース(血管)が太くなると圧が下がる、みたいなイメージですね。
ホース(血管)が太くなると圧が下がる、みたいなイメージですね。
薬剤師
その通り。加えて、臓器を守る効果が期待できる薬もあるので、数字だけでなく“守る”視点も大切です。
その通り。加えて、臓器を守る効果が期待できる薬もあるので、数字だけでなく“守る”視点も大切です。
1⃣ 血管を広げるタイプ
主な薬:カルシウム拮抗薬(アムロジピン、ニフェジピン 等)/ACE阻害薬(エナラプリル 等)/ARB(ロサルタン、テルミサルタン 等)
しくみ:血管の筋肉が縮む合図をブロックして、血管径を拡げる → 圧が下がる
しくみ:血管の筋肉が縮む合図をブロックして、血管径を拡げる → 圧が下がる
- カルシウム拮抗薬 立ち上がりが比較的早い。むくみ・ほてりに注意。
- ACE阻害薬 アンジオテンシンII産生を抑制。空咳が出ることあり。
- ARB 受容体ブロックで血管を広げる。空咳は少ないが、カリウム上昇に注意。
2⃣ 心臓の働きをゆるめるタイプ
主な薬:β遮断薬(ビソプロロール、アテノロール 等)
しくみ:心拍・収縮力を落として心臓のポンプ圧を下げる
しくみ:心拍・収縮力を落として心臓のポンプ圧を下げる
- 狭心症・不整脈・心不全の合併に有用な場面あり。
- 徐脈、気管支喘息の方は適応・用量に注意。だるさ・冷感を感じることも。
3⃣ 体の水分を減らすタイプ(利尿薬)
主な薬:サイアザイド系(ヒドロクロロチアジド 等)/ループ利尿薬(フロセミド 等)
しくみ:尿量を増やして血液量を減らし、圧を下げる
しくみ:尿量を増やして血液量を減らし、圧を下げる
- サイアザイド系 高齢者にも使いやすいが、低Na/低Kになりやすいので定期採血を。
- ループ 浮腫・心不全で力を発揮。長期の純降圧目的ではやや限定的。
4⃣ 神経の指令を弱めるタイプ
主な薬:中枢性(メチルドパ、クロニジン 等)/α遮断薬(ドキサゾシン 等)
しくみ:交感神経の「上げる合図」を弱め、血管を広げる
しくみ:交感神経の「上げる合図」を弱め、血管を広げる
- 中枢性は眠気・だるさに注意。
- α遮断薬は排尿症状の改善にも使われるが、立ちくらみに留意。
サッと比較:どれがどう効く?
| 群 | 代表薬 | 主な作用 | よくある副作用 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 血管拡張 | アムロジピン/ロサルタン 等 | 血管平滑筋をゆるめ圧低下 | むくみ、ほてり/空咳(ACE) | 初回から効きを実感しやすい |
| 心拍出↓ | ビソプロロール 等 | 心拍・収縮力を抑制 | 徐脈、だるさ、冷感 | 心臓疾患合併で有用 |
| 利尿 | HCTZ/フロセミド | 血液量を減らす | 低K・低Na、脱水 | 採血フォローが鍵 |
| 神経調整 | ドキサゾシン 等 | 交感神経の合図↓ | 立ちくらみ、眠気 | 排尿症状にプラス効果 |
続けるコツ:自己管理のポイント
- 時間を固定:朝食後など、毎日同じタイミングに。
- 急にやめない:自己判断の中断はリバウンド上昇の原因。
- 血圧手帳:朝晩・1〜2回/回を記録し、受診時に共有。
- 副作用は相談:むくみ・咳・立ちくらみ等は我慢せず伝える。
- 相互作用:市販薬・サプリも含め、追加前に薬剤師へ。
覚えておきたい一言:降圧薬は数字を下げる薬であると同時に、脳・心臓・腎臓を守る薬です。